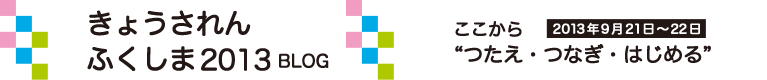全盲のマラソンランナー・福島市の星純平さん(37)から、興奮ぎみに電話がありました。
「今日、白石蔵王ハーフマラソンを走って来ました。昨年よりタイムは5分縮めました。でも今日は、それ以上に嬉しい事がありました」と。
星純平さんは、2年前にマラソンを始めました。
目指すは「サブ・スリー 」。
サブ・スリーは、マラソンを3時間以内で走ること。アマチュアランナーの5%しか達成できず、目標であり夢。
しかし、星純平さんのように伴走者を必要とする視覚障害者には、かなり高いハードルとなっています。
9月初旬、北京オリンピックマラソン代表の佐藤敦之選手に桧原湖畔で2日間にわたって指導を受けた星純平さんは、今回の白石蔵王ハーフマラソンに自信を持って臨みました。
その成果が出たのがスタートから8キロ過ぎでした。
伴走者の中村さんが言いました。
「純平さん!こんなに速いペース、俺ついていけないよ。今キロ3分45秒だよ。伴走は、10キロまでが限界だよ」
それを聞いて純平さんはビックリしました。
なぜならば、純平さんは1キロ4分30秒のペースで走っているつもりだったからです。
自分の思っていたペースより45秒も速く走り、さらにかなり体に余裕があることに、純平さんは改めて驚くとともに、佐藤敦之選手の指導力の高さと効果に、オリンピックを目指すアスリートのレベルの高さを実感しました。
その時、伴走者の中村さんが横を走っていた一人の青年に声をかけました。
「お兄さん、速いね。もし可能だったら、10キロから15キロまでの5キロを、私の代わりこの人の伴走してもらえないでしょうか?」。
青年は、少しはにかんだように言いました。
「ぼ、ぼ、ぼくで良かったら、喜んで」
青年は地元の養護学校を卒業した25歳の知的障害者でした。
菊地さんといいます。
菊地さんは、星純平さんの予想を上回るペースで、純平さんを引っ張ってくれました。
約束の15キロで菊さんは、「ゴールで待ってます」と言い残し、あっという間に駆けていきました。
15キロからゴールまでは、いつも純平さんをサポートしている斉藤さんが伴走を担当しました。
斉藤さんとゴールした星純平さんを待っていたのは、菊地さんの満面の笑顔でした。
隣には、息子が無理やり伴走をかってでたと思い込んでいた菊地さんのお母さんが心配そうに立っていました。
握手を求めて礼を言う純平さんに菊地さんは、「僕はいつも誰かの世話になっています。だから、困っている人がいたら、助けてあげたいんです」と、たどたどしいが、しっかりとした口調でいいました。
視覚障害者を知的障害者がサポートして走る姿に、日本の進むべき未来の福祉やスポーツ、社会のあり方を重ねて、胸が熱くなりました。
星純平さんと菊地さんをつなぐ一本の輪を、純平さんは「絆」と呼んでいます。
2012年9月26日 |
福島市
神奈川県の黒岩知事にインタビューしました。
神奈川県が、「被災地の瓦礫を受け入れる」と表明したことに関し黒岩知事は、「その直後から市民グループや地元の企業から強固な反対にあって進展せず、白紙撤回に近い状態になっていると」と苦悩を話してくれました。
宮城、岩手の瓦礫でさえ受け入れに難色を示している自治体が多い中で、福島県の放射性廃棄物を含む瓦礫を受け入れてくれる自治体などあるはずがありません。
細野大臣は「最終処分場は県外に」と明言しましたが、法制化もされていない現在、その言葉を信じることは出来ません。
中間貯蔵施設が最終処分場になることは明白です。
震災から1年6ヶ月を過ぎた今、未だに場所さえ決まっていない廃棄物中間貯蔵施設。
このままでは除染も進みません。
県は中間貯蔵施設の場所も含め、当事者である双葉8町村にこの問題を丸投げせず、リーダーシップを発揮して欲しいと願っています。
また、そうしないと福島県の復興、復旧はあり得ないと思っています。
2012年9月26日 |
その他
話題の本を紹介します。
震災直後から、相双地方の医療支援に当たっている、東京大学医科学研究所特任教授の上昌広先生が、福島での活動をまとめた本を出しました。
私の事も、ちょっとだけ出ています。
以下、上先生からのメールを転送します・
各位
いつも大変お世話になっています。昨年三月以来、福島県での活動を続けています。
このたび、7月20日に福島での活動をまとめた本を出版しました。できるだけ具体的に、現地で見たこと、聞いたことを紹介させていただきました。地元の方から支援の大学生まで、個々の活動を取り上げています。
後半では、福島復興のために教育を通じた人材養成が必要であり、医学部新設はその一環で考えるべきとの意見を書きました。
是非、お読み頂ければ幸いです。
『復興は現場から動き出す』 上昌広著
東洋経済新報社
2012年9月26日 |
その他
会津若松市の仮設住宅を訪ねた。
浪江町から避難してきた人達が、肩を寄せ合って生きている。
2011年3月11日(金)午後2時46分、マグニチュード9の大地震が東北を襲った。
その40分後、大津波が全てを奪っていった。
9月25日現在、震災による福島県の死者は、2900人、行方不明者は211人。
浪江町では345人の死亡が確認されている。
私が訪ねたAさん(72歳・男性)は、浪江町役場から西へ500メートルの地点で食堂を営んでいた。
3月に開店したので「やよい食堂」と名付けた。浪江焼きそばやラーメンが人気メニューだった。
3月に開店し、45年間続いた「やよい食堂」は、3月に閉店した。
・3月12日午後4時前、東京電力福島第一原子力発電所で水素爆発が起きた。
直後、浪江全町民に避難命令が出された。Aさんは家族5人で、浪江町津島に逃げた。
ここに3日間いた。あとで知ったが、津島地区は放射線量が高かった。当時50マイクロシーベルトと発表されていた。
50マイクロシーベルトが何を意味するのか、全く分からなかった。
その後Aさんは、川俣町~大宮~福島市~会津若松市と避難を繰り返し、6回目の引越しを経て、会津若松市の仮設住宅に落ち着いた。
警戒区域となっている故郷・浪江には、これまで5回一時帰宅した。雑草をかき分けて自宅に入った。
余震の影響で壁が崩れ、雨漏りの影響か、畳はかびて悪臭が鼻をつく。
動物に荒らされた台所は、腐った食品が散乱していた。
Aさんは、「もう住めないな」と思った。
墓参りのため菩提寺に行った。墓石は全て倒れていた。納骨堂も傾き、開いた扉から骨壷が地面に落ち、遺骨がさらされていた。
Aさんは思わず手を合わせた。
震災から1年6ヶ月。Aさんは「疲れてた」を連発するようになった。体力も気力も萎えていくのを感じている。
・今年5月27日、避難先から一時帰宅で浪江町に入っていた62歳の男性が、自宅倉庫で自ら命を絶った。
Aさんの友人だった。
自殺した男性は生前、避難生活のストレスや経済的な不安で眠れない日が多いと訴えていた。
Aさんは言う。「浪江町の住民で自殺した人を何人も知っている。避難生活中に病死した人もたくさんいる」
「これは全部、原発に殺されたんだ」と。
・7月16日に名古屋市で開催された「エネルギー・環境の選択肢に関する意見調査会」で、中部電力原子力部の男性課長(46)が個人的な意見として言った。
「福島の原発事故の放射能で亡くなった人は一人もいない。今後5、10年たっても変わらない」
「政府は原子力のリスクを過大評価している。このままでは日本は衰退していく」と。
彼は、福島に来たことがあるのだろうか!
・福島では今、原発事故により、無理な避難生活を強いられ、未来に希望を持てない人がたくさんいる。
一日中、仮設住宅に引きこもっている人。ストレスや運動不足から高血圧や肥満になり、糖尿病患者も急増している。
認知症も進むケースが顕著だ。
そして、何よりも生き甲斐をなくしてしまった人が多い。
岩手・宮城・福島の被災3県の中で、「震災関連死」も福島県が突出している。
政府の対応の遅れが、福島県民を殺しているのだ。
『野田総理、東電社長、福島に来て原発事故で苦しむ県民の声を聞け!』
2012年9月26日 |
浪江町
須賀川市の有馬信二くん(26)とご両親です。

信二くんは、地元の高校を卒業して就職。
出社初日に自宅で倒れ、意識を失い、寝たきりになりました。
あれから8年。
優しい家族に支えられ、
喜怒哀楽を表すまでに
回復しました。
この日は、ご両親と一緒に私の講演会の会場 を訪ねてくれました。
顔色が良くて安心しました。
信二くんは、ラジオから流れる私の声に反応し、
笑うそうです。
「大和田さんの放送に元気をもらっています」と信二君のお母さんがおっしゃっていました。
とても嬉しい一言です。
信二くんは私の下ネタが大好きだそうです。
信二くんの為にこれからも幸せホルモン「セロトニン」より「エロトニン」大放出で頑張ります。
2012年9月26日 |
須賀川市
« 前の記事
新しい記事 »