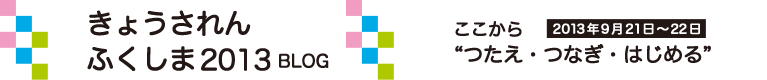第616話 相馬高校土曜講座を担当して(3)~教室に高校生の声が響きわたった群読の授業
聖光学院中学・高等学校国語科教諭
野中 潤
2013年10月5日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行
8月30日の夕刻に相馬に到着した私は、翌31日の午前9時から約2時間、福島県立相馬高校で国語の授業をしてきました。与えられた120分間でどのような授業をしたらよいのか、そもそも相馬の高校生たちがいま何を求め、何を考えているのかが全くわからない状況でしたから、話が決まった時はいろいろと思い悩みました。やり直しのきかない一度限りの授業であるだけに、考えれば考えるほど不安は募るばかりでした。それでも自分にできることはいったい何かということをつきつめていったら、彼らと私とのあいだに言葉を置いて、120分の時間が流れる中でそれらの言葉を少しでも共有することができればそれでよいのではないかと考えるに至りました。選択したのは「群読」の授業です。
群読というのは、一つのテキストをグループで朗読する活動で、どこを誰が読むのか、2人で読むのか3人で読むのか全員で読むのかということを、生徒たちが考え、練習を繰り返して発表をする学習活動です。私は近現代詩をテキストに選び、誰がどこにどのように立つのか、読むときの表情や視線を含め、詩の世界をより豊かに表現する方法をグループの話し合いとリハーサルを通して生徒たちに模索させています。120分というのは、群読をするためには十分な時間とは言えませんが、いつもとは違う工夫をいくつか盛り込んで、何とか授業を成立させることができました。
相馬高校の小野田義和先生の案内で教室に向かい、私のことを紹介して頂き、朝の挨拶もそこそこに、まずは生徒たちを教室の前に立たせ、アイスブレイクを兼ねて発声練習をしました。
「マメモ、ラレロ、パペポ…」
「アメンボ赤いな。ア、イ、ウ、エ、オ。浮藻に小エビも泳いでる…」
お手本を示す私に続いて、生徒たちが声を合わせて発声します。「ブラジル人のミラクルビラ配り」のような早口言葉をはさみ、北原白秋の「五十音」を「ずりずり頬ずりヒゲ親父。ごりごり骨太ゴリマッチョ。ラミパスラミパスルルルル…」などと逸脱させて遊びました。
相馬高校の生徒たちは、いきなり発声練習を強いられたにもかかわらず、始めから元気に声を出してくれ、笑顔が広がりました。私の不安は一気に吹き飛びました。
そのあと、いくつかの詩の載せたプリントを配りました。そこには、たとえばこんな詩が印刷されていました。
月夜の浜辺 中原中也
月夜の晩に ボタンが一つ波打際に 落ちていた。
それを拾って、役立てようと僕は思ったわけでもないが、 なぜだかそれを捨てるに忍びず、 僕はそれを、袂に入れた。
月夜の晩に、ボタンが一つ 波打際に、落ちていた。
それを拾って、役立てようと 僕は思ったわけでもないが、 月に向かってそれは放れず、 浪に向かってそれは放れず、 僕はそれを、袂に入れた。
月夜の晩に、拾ったボタンは 指先に沁み、心に沁みた。
月夜の晩に、拾ったボタンは どうしてそれが、捨てられようか。
中原中也(1907-1937)の「月夜の浜辺」は、私自身がこれまでに何度も群読の授業で取りあげたことのある詩です。童謡や歌謡曲のような平明なリズムの口語定型詩ですが、その言葉の端々に「僕」の哀切な思いがにじみ出ています。今回の群読では、この詩のほかに、高見順(1907-1965)の「われは草なり」と町田康(1962-)の「うどんを食べたい」(
http://www.machidakou.com/lyric/ )を取り上げました。
これらの詩について、修辞法を分析するとか、言葉の置きかえという形で解釈を試みるとか、作者の気持ちを想像するとかという形で行われるのが通常の国語の授業です。
しかし今回はそのような「まわり道」をせずに、とにかく声に出してくり返し詩を読んでもらいました。ただただ仲間と一緒に声に出して読むこと、どういう風に声を合わせて読めばよいのかを考えることだけに意を注ぎ、詩の言葉とじかに向き合ってもらいました。
結果として120分間、相馬高校の生徒たちの声が教室に響きわたり、同じ詩を何度も何度も声を通して味わう体験をすることができました。1人で読むところ、2人で読むところ、全員で読むところなどの効果的な分担の仕方を話し合い、読むスピードやリズムを工夫し、立ち位置や身ぶりを考えてくれました。短い時間ではありましたが、私の授業を真っ直ぐに受け止めて、群読を存分に楽しんでくれました。
「月夜の浜辺」のような詩を読むことについて、もしかすると相馬の高校生たちが拒絶反応を示すかもしれないという危惧もあったのですが、読んでみたいと手を上げてくれる生徒たちがいて、私の心配は杞憂に終わりました。3つの詩について、私からは特別な説明は何もしませんでした。それでも、出会うことと別れること、生きることと死ぬこと、孤独であることと共に生きることなど、相馬高校の生徒たちは私が持ち込んだ詩の精髄を鋭敏に感じ取り、聞く者の胸にじかに響いてくるような見事な声を響かせてくれました。予想をはるかに超えた素晴らしい群読でした。
発表が終わった後、私は少しだけ時間をもらって、彼らに語りかけました。
言葉が使い捨てになりがちな昨今、くり返し読むに耐える強度をもった言葉を見つけて、何度も同じ言葉に向き合う体験を持つことの大切さについて話しました。
中原中也や高見順はすでに物故してしまっているけれども、こうして詩を読むことによって、彼らの思いが「いま・ここ」によみがえるのだということを語りました。
そんな風にして、時空を超えて人と人とを繋げるところに、文学の素晴らしさがあるのだということを訴えました。
それから、声を和することは人間が「いま・ここ」にともにあることの喜びを感じるための手立ての一つであり、そういう形で時間と空間を共有できてとてもうれしかったということを伝えました。
震災の年の6月に高校生20人とともに汚泥除去作業をするために岩手県の宮古市を訪れて以来の「被災地」訪問でしたが、相馬市でも南相馬市でも浪江町でも、集落ごとに様相を異にすると言っても過言ではないくらいに、さまざまな光景を目の当たりにしました。美しく整備された相馬野馬追会場の雲雀ヶ丘祭場地、メガソーラー発電設備を計画中だという原町火力発電所、54人の犠牲者の名前が刻まれた真新しい慰霊碑が建つみちのく鹿島球場、夏草に埋もれかけている常磐線の赤錆びた線路、募集を停止し休校状態で生徒の姿が消えた私立松栄高校など、いくつもの印象的な光景が脳裏に刻まれています。見えてくる光景のすべてが福島の現実でした。
相馬中央病院の西川佳孝先生や新地高校の高村泰広先生など、厳しい現実に向き合いながら日々を送っている方々にお目にかかり、貴重なお話をうかがうことができました。東大の院生として南相馬市立総合病院などで継続的に支援活動を続けて来た教え子の野村周平君との再会を果たすこともできました。
それらの体験について、またその折に私が感じたことについて、ここで詳しく語る余裕はありませんが、印象に残った光景を1つだけ書き留めておきます。
群読の授業をした日の午後に、学習評価研究所の松浦三郎先生とともに、地元の方の案内で浪江町の請戸集落を訪れました。福島第一原発まで6キロほどの広大な平地は、請戸漁港から流されてきた漁船と津波に耐えた家が何軒か見えている以外は、茫漠とした原野と化していました。雑草が生い茂った原野を貫く県道254号線に車の姿はありません。インターネットで見たことがある、折れ曲がったまま放置された電柱が目の前にありました。その先には、福島第一原発の排気筒がはっきりと見えています。線量計は、0.4~0.5μ?/hぐらいの数値を示していました。
空は晴れて、わずかに風が吹いています。私たちの他には誰もいません。信じられないくらいの静寂が、広大な空間を満たしています。
茫漠たる空間の真ん中あたり、十字路の一角に建つ真新しい慰霊碑の前で、真っ直ぐに海へと続くアスファルトの道を眺めながら、私はじつはこの静寂と正反対のものを求めて群読の授業をしていたのだなと気づかされました。
群読の授業を終えて教室を後にするとき、「どうもありがとうございました!」とか「ノナカ先生! さようなら」などと笑顔で声をかけてくれた相馬高校の生徒たちの心の中 をつぶさにうかがい知ることはできませんが、授業後に受け取った感想文には私を喜ばせるような言葉がたくさん書き込まれていました。私にとっては忘れがたい体験となった今回の群読の授業が、彼らの心にも何かしら肯定的な感触をともなう記憶となって残っていてくれることを願っています。
略歴:横浜の聖光学院中学高等学校国語科教諭。1962年生まれ。中央大学大学院兼任講師、日本大学文理学部非常勤講師。主著は『横光利一と敗戦後文学』。近年は「定番教材の誕生」(
http://www.chikumashobo.co.jp/kyoukasho/tsuushin/rensai/teiban-kyouzai/001-01.html )
など、サバイバーズ・ギルトという観点から文学を読み直す試みを展開している。
今回の記事は転送歓迎します。その際にはMRICの記事である旨ご紹介いただけましたら幸いです。
MRIC by 医療ガバナンス学会
2013年10月6日 | その他