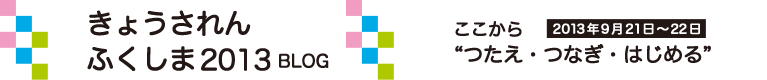第531話 医療支援者からの“相馬野馬追( そうまのまおい) ”への想い
医療支援者からの“相馬野馬追(そうまのまおい)”への想い
南相馬市立総合病院・神経内科
小鷹 昌明
2013年8月20日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行
国の重要無形民俗文化財であり、この土地の最大行事である“相馬野馬追”に参加した。
これは、相馬氏の祖といわれている平将門が下総国(千葉県北西部)に野馬を放ち、敵兵に見立てて軍事訓練を行ったことが始まりと伝えられている。千有余年の歴史を有し、史跡中村跡での総大将の出陣式を皮切りに、500余騎(今年は410騎)の騎馬武者たちが勇壮な戦国絵巻を繰り広げるのである。
開催期間中に、延べ16万6,500人の観光客が、この野馬追見学に訪れた(前年比6,500人増)。これは平成13年以降最多であり、すなわち、「規模としては、概ね震災前に復した」ということである。
> 今年は縁あって、その伝統行事に参加した。
振り返ってみれば昨年の今日、私は雲雀ヶ原祭場地からこの祭典を眺めていた。遥か遠方からの距離ではあったが、それでも甲冑(かっちゅう)に身を固め、太刀を帯び、先祖伝来の旗(はた)指物(さしもの)を背負い、威風堂々にして豪華絢爛な進軍には、誇りのようなものを感じたし、白鉢巻を締めた騎馬武者が、砂埃舞うなかを人馬一体となり、旗をなびかせて勇壮果敢に疾走する迫力には、とことん魅了された。猛暑のなかでの格闘であり、男たちの晴れ姿が、目の前に広がっていた。伝統と文化としての格式が、そこには確かにあった。
観戦を終えた帰り道、得も言えぬ思いが込み上げ、私は「来年は、何はともあれ出てみたい」と思った。ふつふつとしたその願いは、半年間以上絶えることがなかったので、野馬追に代々参加している地元住人に、思い切って相談してみた。
「馬には乗れないので歩くだけでいいのですが、昨年移住した人間を、いきなり出してもらうことなどできるでしょうか?」と。もっともそれは、年が明け、さらには冬も終わろうとしてからのことだった。
結局私は、「出てみたい」とは願ったものの、乗馬経験のないハンディに対して、短期間で馬を乗りこなすことなど到底できるものではないと思ったし、それを覚悟で挑戦してみるという自信もなかった。だから、徒歩による進軍を希望したのだが、それは、見栄を張るなら一応は控えめに、伝統の邪魔にならない範囲での打診であった。
ところが地元の人は、「もちろん出られますよ、大歓迎です。でも先生、どうせ出るのなら、ぜひ馬に乗ってください。いまからでもしっかり練習すれば大丈夫ですから」と説明された。それは、ありがたい一言だった。そして、その後も馬に乗るよう何度も勧められた。
しかし、最後まで行動を起こすことはなかった。きっと私は、野馬追に関与する気合いをそれほど強くは持っていなかったのだろうし、少し体験させていただくだけで充分と思っていたのである。だから、周囲に打ち明けることもなかったし、自分のなかでのみ満足すれば、「それでいい」と思っていたのである。
そんなつもりだったのだが、祭日が近づくにつれて状況は変わっていった。
「市立病院の医師3人が、どうやら“野馬追”に出るらしい」という噂が広がり、地元のFM局や新聞社が取材に来たのである。聞くところによると、病院職員が野馬追に参加するのは初めてのことのようで、特に「県外からの支援部隊が地元の伝統行事に列する」という事実に、関心を寄せる人が多くいたのである。
それは私にとって意外なことであり、良くも悪くも大きな意味を持つものだった。
この地域においての市立病院という組織は、“一団体における職員数”という点では、かなり多い方なのではないか。その人数をもってしても、野馬追”というものに、これまで出たことのない集団だったのである。
いや、何も「病院職員は、“野馬追”に関心がない組織である」と言うつもりはない。現に、行事が近づけば、それをテーマとする会話は日常的だったし、「夫が野馬追に出陣する」という看護師もいた。当日の沿道には多くの病院関係者がいて、私のようなものに対しても声援を送ってくれた。
だから、「出たいという人が、たまたまいなかった」というだけの理由のようにもみえるが、そこがまさにその通りで、要するに、積極的に出ようとする人間がいなかったのである。
それはきっと、「野馬追は祭ではない」という意識があるのではないか。あくまで、それは伝統行事であり、もっと言うなら神事である。「こうしたイベントに参加する人というのは、ある程度限られた系統的な人間である。親族で出ている人などいないのだから、私には関係ない」という感覚がある。
市立病院から野馬追に参加した3人の医師は、私を含めていずれも、福島には縁のない県外からの支援医師だった。そして、私たちは、とりあえずは勧められたわけでなく自分の意志で、独自のルートを通じて参加を表明した。土着的な気質もなく、しがらみもない、こう言っては批判されるかもしれないが、出たいから出た。
そうした私たちのこの行動を、地元取材陣の多くは「支援に駆けつけていただいていた医者が、伝統行事に出陣されるのは嬉しく、ありがたいものである」と伝えてくれたなかで、「支援の名のもとに誰でも参加できるイベントとなり、“相馬野馬追”の伝統と格式が失われていくのを危惧している。千年を超える伝統には、守るべきもの、譲れないものがあるはず」というような意見も寄せられた。
なるほど、野馬追における意見として正論であろうことは理解できる。確かに私は、「それほどの伝統を重んじ、それを背負って参加しよう」などという、そこまでの気負いはなかったかもしれない。「馬には乗れないので、歩くだけ」というのも、「なめているのか」と思われても仕方のない部分があったかもしれない。
しかし、何はともあれ、とにかく参加したかったのである。甲冑を着てみたいとか、目立ちたいとか、そういう気持ちがないと言えば嘘になるかもしれないが、とにかく出てみたかったのである。この土地で一千余年にわたる”野馬追”がいかなるものなのか、よくわからないので、少しでもわかるためには「出るしかない」と思ったのである。
「出てもいないものがとやかく言う資格はない」という意見があったとしたら、それもひとつの正論だと思う。だから、野馬追を感じる人間になりたいと願い、語ることのできる資格を与えてもらうために参加を考えたのである。そういう形での「伝統の継承」というのもあるのではないか。
当日、私は正式でない場ではあるが、甲冑を着て馬を駆ることができた。そして、“お行列”に参加することができた。乗馬経験のなかった私は、結局、馬丁(ばてい)(正式には中間(ちゅうげん))として「功労者の馬を引く」という役割を与えられて、進軍に加わった。沿道を埋め尽くす多くの観光客と地元市民のなかを、私は歩いた。
伝統的な野馬追だからこそ、その見物には驚くべき御法度があった。“お行列”を横切ってはいけない、2階などの上から見物してもいけないのである。野馬追とは、相馬武士の心意気を現代に伝える神事であることから、これらの行為は、昔で言うところの大名行列を横切ったり、上から見下したりする無礼な行為と同じなのである。つい数年前までは、階上からの見物客 を見つけると、武者が土足で家に上がり込み、引き摺り下ろされたそうである。相馬武士は、伊達政宗を相手に一歩も引かなかった果敢さで知られていることから、出場者は“完全武士”になるのである。
その行群の一部に加わった。言い方は難しいが、それは私にとっては、とてもとても優雅な、そして、日常を忘れさせる刺激的な時間だった。そして、歩きながら私は、被災地ではあるが、喚起溢れる南相馬市のまだまだ残されているポテンシャルを感じた。
野馬追でやるべきことは、戦国時代からの変わらぬ伝習を守り、再現することである。鎧兜で身を締め、太刀を携え、先祖伝来の旗を翻し、馬を乗りこなせば普段と違う自分がそこにいる。地震や津波や原発とは関係のない、昔からの自身を立ち上げることができる。「地に足が着く」というか、「戻るべき原点に立ち返る」というか、もっと言うなら、単純に「血がたぎる」というような感覚に浸れる。
本祭りのハイライトである“甲冑競馬”と“神旗争奪戦”とを、今年は祭場内の陣営の前に鎮座したうえで間近で観戦した。「伝統だ」とか、「格式だ」とかいう以前に、純粋に「格好いい!」と思った。武士としての振る舞いの勇ましさに、ただ酔いしれた。
私は、馬に乗らなかったことを心底悔やんだ。そして、ますますこの土地が好きになり、復興のための活力が湧いた。それが、“野馬追”が私に与えてくれた最大の効果であった。
祭の終わる頃、私は「来年は馬に乗ろう」と決めた。
2013年8月20日 | その他